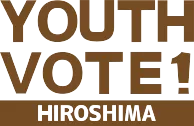今回は、東広島市議会の木村輝江議員にインタビュー。
子育て世代の声を届けたいと立ち上がった背景や、議員活動を支える周囲の存在、そしてまちづくりへの想いについて伺いました。
アフタートークを含む全編動画はこちらからどうぞ。
目次
木村 輝江
1983年、宮崎県高千穂町生まれ。宮崎県立高千穂高校を卒業後、筑紫医師会の看護学校に進学し、看護職員として医療機関や介護施設で12年間勤務。結婚を機に東広島市高屋町へ移住。2023年、東広島市議会議員選挙に出馬し初当選。取材時現在、東広島市議会議員1期目。4児の母。
政治は遠い存在だった学生時代
学生の頃から、そして子どもが生まれてからも、政治は自分にとって本当に遠いものだったんです。
選挙があることが分かっていても、正直、必ずしも毎回投票に行ったかというとそうではなかったですし、行ったとしても、候補者がどんな政策を掲げているのかも分かっていませんでした。
それくらい関心がなかったんです。そんな私が議員になろうと思ったのは、「母親としての声」と「地域の声」をしっかり届けたいと思ったからです。当選して議員として活動する今もこの想いを強く持っています。
子育てひろばの閉鎖で感じた“届かない声”
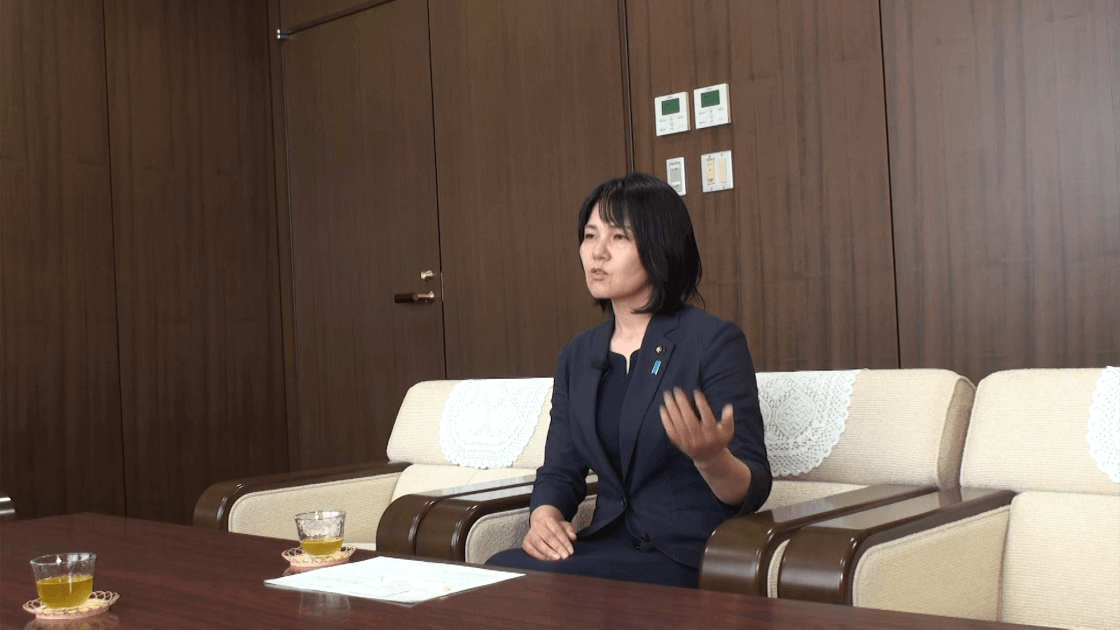
母親として「私たちの声を届けたい」と思った最初のきっかけは、市の子育てひろばの閉鎖でした。1月に「年度末で閉鎖します」と急に聞かされて、実質閉鎖まで2か月ほどしかない状況だったんです。
そこは、乳幼児だけでなく小学生も利用できる室内の遊び場だったんです。しかし、同じような場所は、市内の中心部にはそのひろばしかありませんでした。だからこそ、子育て中の親にとっても、子どもたちにとっても大きなダメージで、「これは困る」と強く感じました。
そこで、当時の市議会議員に相談をして、署名を集めて市長に届けるという行動をとったんです。
ただ、淡々と要望を伝えたつもりでも、なかなか想いが届かないと感じました。
もしかしたら、お話を聞いてくださった方が子育てを一通り終えていたこともあり、当事者の切実さまでは伝わらなかったのかもしれません。
今、子育てをしている人の意見をどう届けるのか。当事者ではない人にとっては要望にしか聞こえず、願いとしての重みは伝わらないのだと実感しました。
だからこそ、政治に参加する意味として「意見をどう届けるか」が大切で、自分がその代弁者になれたらと思うようになったんです。
振り返ると、その気持ちを強く意識したのは選挙の半年前くらい。ほんの短い期間でした。「私でいいのかな」と迷いもありました。でも同時に、子育てひろばの閉鎖のことを思い返して、今の子育て世代の目線を持つ議員が必要なんじゃないかと感じたんです。
閉鎖の決定を「急に知らされた」と感じた一方で、実際には委員会で議論され、市からも発信されていたはず。でも私たちはそれをキャッチできていなかった。住んでいる町のことなのに見えていなかったのです。
それは単に関心や興味の問題ではなく、情報を届けてくれる人がいなかったからだと思います。身近な同世代や、同じように子育てをしている議員がいないことも大きいと感じました。困ったとき、私たちはつい「不満を言う」だけで終わってしまいがちですよね。友だち同士で「こんなことがあるんだよ」「困ったよね」と話しても、「じゃあどうしようか」とまではなかなかならない。
でも、もし身近に「聞いてみよう」と思える議員がいたら、相談して一緒に考えるきっかけになって、もっと幅広い施策につながるんじゃないかと考えるようになりました。
一人ではできなかった第一歩

議員を目指すことになった最初のきっかけは、夫のひとことでした。「4月に選挙があるよ。やってみたら?」と声をかけてもらったんです。
でも当時の私は、政治に本当に興味がなくて。ニュースを見ても流れているだけで気に留めたこともなく、知識もない状態。「私じゃない、誰かがやること」と思っていました。
つい「誰かがやってくれる」と思ってしまいがちですが、それがいつになるかは分からない。そう考えたときに、せっかく夫も応援してくれているし、時期も迫っているという状況で。母親の声を届けたいという思いを形にするチャンスだと感じました。
自分が議員になることで、同世代や子どもたちにとって政治を考えるきっかけになるかもしれない。
そう思って挑戦を決意しました。
夫や同居する両親は「やったらいいじゃない」と後押ししてくれました。ただ私は宮崎県出身で、夫の地元に移り住んできたとはいえ、東広島での地縁はほとんどありません。子育て中心の生活をしてきて、地域の役を担った経験もなく、知名度もゼロ。
そのような状況で「どうしたらいいのか」と悩みながらも、思い切って私、ずっとタスキを着けたまま生活してたんです。そのタスキには「4児の母」と書かれていて、幼稚園の送迎やスーパーでも、その姿のままで歩いていました。声をかけられた人に「実はこういうことに挑戦しようと思っているんです」と伝えると、「何をしたいの?」と聞いてくださる方もいました。
「子育て支援を充実させたい」と伝えたとき、実は「否定されるかもしれない」と思っていたんです。けれど実際には、思っていた以上に「応援するよ」と受け止めてもらえて、本当に心強く感じました。
そうやってありがたい応援もある一方で、選挙が近づくと人手が必要になります。地域の重鎮にも挨拶には行きましたが、良い反応は得られず、「頼りきるのは違う」と判断しました。
そこで頼ったのは友人たちです。「手伝ってほしい」と思いを伝えると、「この日なら行けるよ」と力を貸してくれる仲間が現れました。そのおかげで選挙期間を乗り越えることができたんです。
また、チラシを急いで作り、自分の子どもが通う小学校区を一軒一軒歩いてポスティングしました。幼稚園に通う子どもを自転車に乗せながら回ることもあり、1日5万歩を歩いた日もありました。大変ではありましたが、自分の思いに共感して支えてくれる人がいたからこそ、最後まで続けられたと思っています。
それから、資金面でも苦労はありました。「選挙にはお金がかかる」と言われますが、私はできるだけコストをかけずに活動しようと決めていたんです。というのも、一人の母親が選挙に出るとなったときに、「これだけ資金が必要です」と言われても、すぐに準備できるものではありません。知識も経験もない私が、無理にお金をかけるよりは、身近な人たちと協力して、できる範囲でやっていこうと思ったんです。
看板のデザインは夫にお願いし、ホームページも二人で相談して作りました。選挙カーの看板も工夫しましたし、ほとんどがボランティアの支えで成り立っていました。
インターネットで調べると「選挙の準備に数百万円かけた」という例も多く見ましたが、私は「お金をかけない選挙」をやりきったんです。
夫は出勤前のランニングに幟旗を背負って走ってくれたので、「夫が出馬するの?」と間違われることもありましたね。そんなふうに家族と一緒に知恵を絞り、工夫を重ねて迎えた挑戦でした。
ホームページやブログでは、自分の背景や政策を伝え続け、できることをとことんやりきった。それが、私にとっての最初の一歩でした。
暮らしの魅力あふれる東広島市へ

私の一番の目的は、この東広島市をより発展させることです。そのためには、「この街に住みたい」と思ってもらえる人を1人でも増やすことが大切だと考えています。
東広島市は創造性や生産性を持つ街であり、大学や大手企業も集まる学術研究都市です。インフラや産業の面では今後もますます発展していく一方で、私は「子育て支援施策がまだ十分ではないのでは」と感じています。
だからこそ、子育て支援の充実を全世代の利益につなげたいという思いで活動しています。
特に力を入れているのが「子どもの居場所づくり」です。市には出産直後から相談や支援を受けられる「ネウボラ」機能がありますが、小学生になると相談できる場所や遊び場がぐっと減ってしまいます。
不登校児童が増えている中で、「学校だけが居場所じゃない」と感じる子もいます。そうした子どもたちにとって「ここがあるから大丈夫」と安心できる場所をつくることは、より良い成長につながるはずです。
また、子育て世代からは「子どもの遊び場が少ない」という声も多く寄せられています。特に室内の遊び場は不足しており、公園でもボール遊び禁止などのルールでおもいきり遊べないこともあります。
新しい施設をつくるには税金がかかりますが、既存の施設を活用すればできることはあるはず。想いをもって活動されている市民のみなさんによるサークルや、子どもの遊び場づくりを進めている団体と連携し、場所や活動を知ってもらえる仕組みを考えているところです。
特に育休退園制度については、制度そのものが子育て支援にも就労支援にもつながっていないと考え、撤廃を求めて一般質問で取り上げました。現在、市も「検討する」と答えてくれています。
全国的に「人口減少や少子化で街の魅力が失われているのでは」と感じています。だからこそ、子育て世代が「ここで暮らしたい」と思える環境を整えることが重要です。具体的には、産科や小児科の不足、育休退園制度といった課題に取り組んできました。
他にも、子どもたちの声を直接聞くことにも力を入れています。でも、タウンミーティングに来るのは関心がある人だけ。だから私は、地域のイベントやマルシェ、公園などで子どもたちに「学校楽しい?」「どんな遊び場が欲しい?」と話しかけるようにしています。
すると「学校に居場所がない」と感じている子や、「大人に相談してね、と言われても言えない」という声も聞こえてきました。そうした背景もあり、私が議員になって最初の一般質問で提案したのが「子どもが気軽に相談できるチャット機能の導入」です。
その後、同僚議員からの提言もあり、孤独・孤立対策の一環として24時間相談できるチャットサービスが立ち上がるなど、少しずつ環境が変わりつつあります。
私が目指すのは「100年先も輝く東広島市」です。そのためには私一人ではなく、議会全体で力を合わせることが必要です。
産業やインフラといったハード面の発展に加え、子育てや教育、居場所づくりなどソフト面の支援を充実させてこそ、本当に魅力ある街になる。そう私は信じています。
若い世代の人たちへ ― 政治は“遠いもの”じゃなく“一緒に考えるもの”

まず、私はこのサイトにアクセスしてくれた時点で、みなさんは「一歩を踏み出している」と思います。
政治は暮らしとつながっている、と大人から言われても、若い世代にとってはなかなか実感しづらいかもしれません。でも日常生活の中で、「なぜこうなんだろう」「ここが少し不便だな」と感じる瞬間は誰にでもあるはずです。
そうした疑問や不安を、そのままにせずに考えてみてほしいと思います。
もちろん、答えがすぐに見つからないことの方が多いでしょう。そんな時は、周りの人に頼ってみてください。「迷惑をかけるかも」と思うかもしれませんが、実際はそうではなく、話すことで相手から新しい情報を得られたり、その想いが広がったりします。頼ることは決して悪いことではありません。
そして、その相談相手の1人に、市議会議員もいるということを知っておいてほしいです。もし機会があれば、気軽に声をかけてもらえたらと思います。
私自身が、母親であり、議員でもありますが、人生とは「体験と経験の連続」だと感じています。選挙に挑戦したことも、大きな経験のひとつでした。日常の中での小さな出来事も含め、どんな経験も自分を形づくるものです。
そうした積み重ねの中で、「自分は何を考え、何を実現したいのか」を少しでも考えて生きることが、人生をより豊かで楽しいものにすると信じています。
だからこそ、若い世代のみなさんには、ぜひいろんなことに挑戦してほしいです。そして、自分の思いや考えを言葉にしてみてください。たった一人でも意見を伝える人が増えるだけで、社会は少しずつ良い方向に変わっていきます。
そういう意味で、政治は決して遠いものではなく、一緒に考え、一緒につくっていけるものだと思っています。
インタビュアーより
今回が初めての「政治家へのインタビュー」だったのですが、実は最初はすごく緊張していました。政治家の方ってもっと堅苦しくて、距離を感じる存在なんだろうなと勝手に想像してしまっていたからです。
ところが木村さんは、そのイメージをいい意味で裏切ってくださる方でした。とても親しみやすく話しやすい方で、むしろこちらが元気をもらえるような雰囲気がありました。
印象的だったのは、母親の視点を大事にしながらも、とてもエネルギッシュに活動されていることです。そして、より広い世代の人たちに政治を届けたいという強い思いも感じられました。お話を伺いながら、「自分たちも頑張らなきゃ」と背中を押していただいたような気持ちになりました。
Youth Vote! HIROSHIMAのインタビュー
Youth Vote! HIROSHIMAでは、以下の2つの目的で政治や選挙の現場に携わる方々にインタビューを実施しています。
- 政治・選挙の現場のリアルを伝えるため
- 政治や選挙に対してのハードルを下げるため
詳細や実施方法、インタビュイー募集については、以下のページをご覧ください。
Youth Vote! HIROSHIMAのインタビューとは
また、他のインタビュー記事については以下をご覧ください!
インタビュー記事の一覧